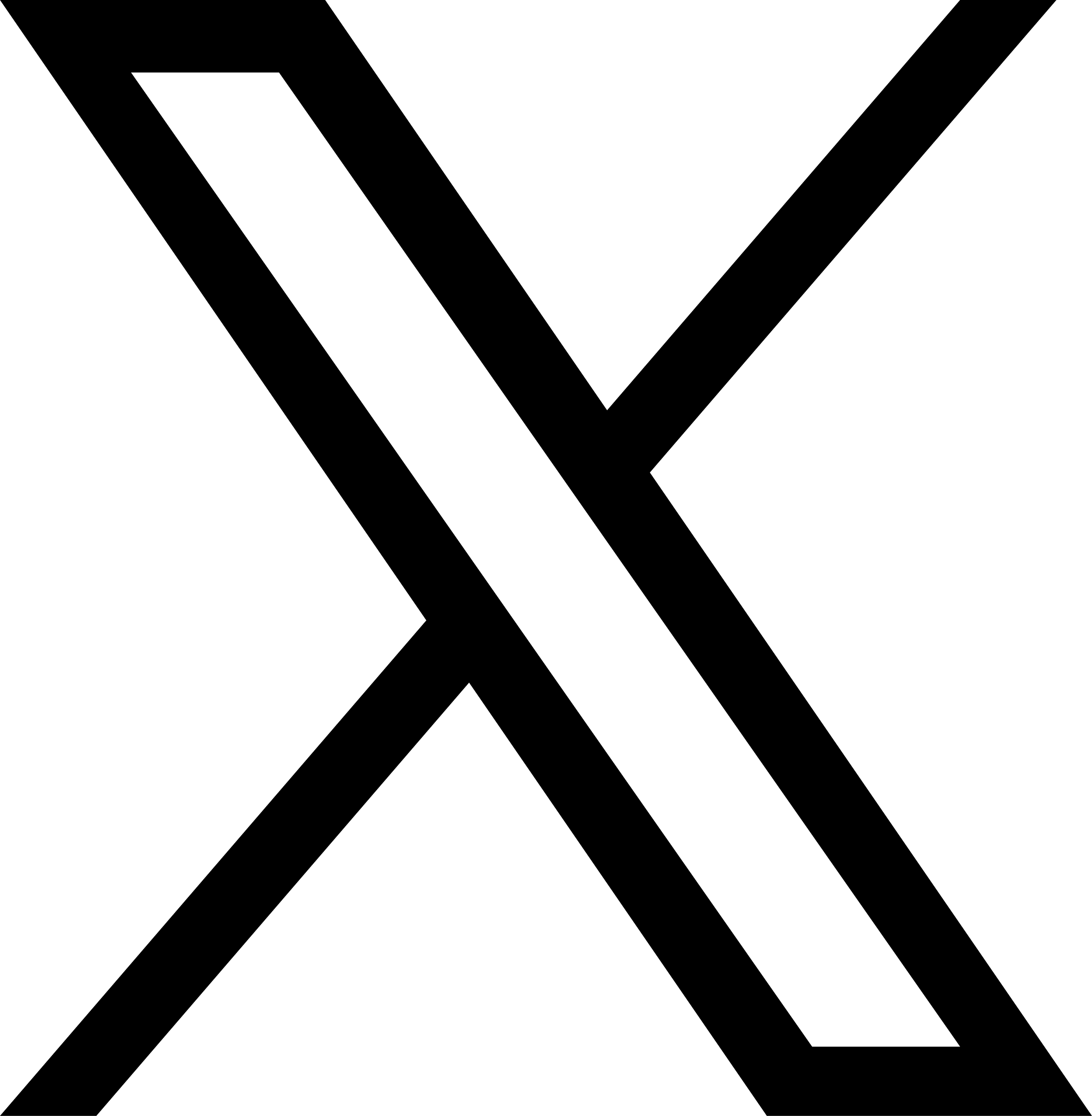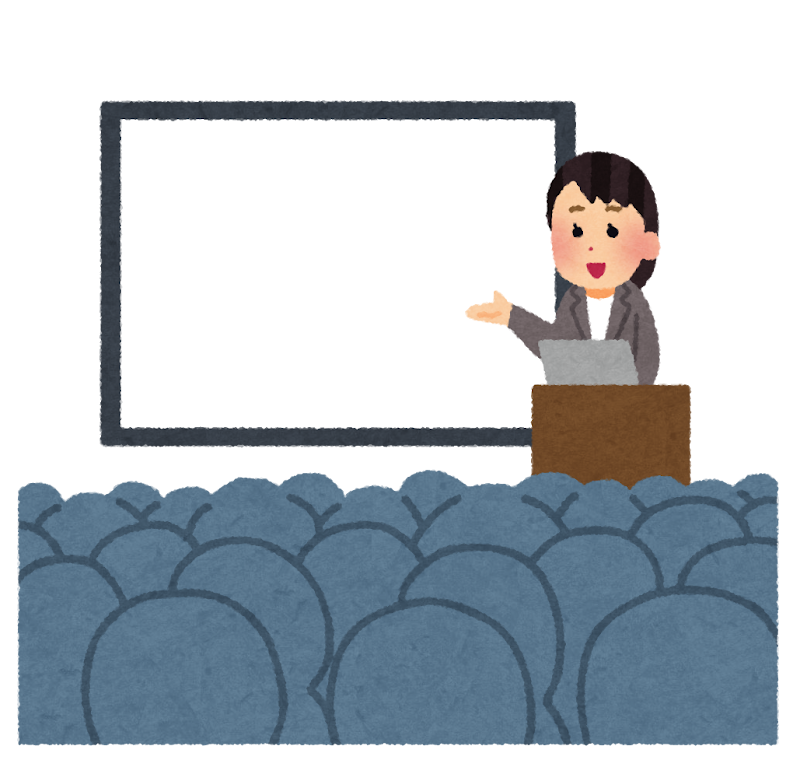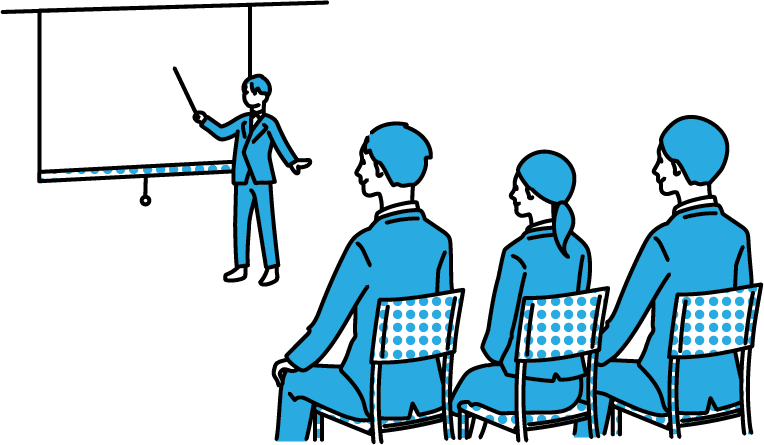取組概要
都市設計・政策では、一部の声高な少数派(ノイジーマイノリティ)の意見を濃く反映してしまうリスクがあります。食品や車メーカーなどと異なり、顧客価値の検証をする例が乏しいため、静かに支持している物言わぬ多数派(サイレントマジョリティ)の意見が可視化されてこなかった背景があります。その結果、一部の強い苦情に影響を受けてしまう例が後を絶ちません。例えば、子どもの声がうるさいとの近隣住民の苦情をきっかけに、公園の廃止や保育園新設の中止という事例があります。除夜の鐘を中止する寺院も報道されています。サイレントマジョリティの存在を無視し、積極的かつ熱心な反対派であるノイジーマイノリティの意見ばかりが反映されると、都市の風情や活気が失われていく懸念があります。そこで、本研究は、公園を対象として、電車の音よりも、鐘の音と子どもの声の方が、魅力があり、訪問意向を高め、街の居住意向に寄与することを科学的アプローチで実証しました。この結果は、日本電気株式会社(NEC)、 hootfolio、 明治大学商学部加藤拓巳准教授の共同研究の成果で、日本感性工学会 優秀発表賞を受賞しました。
成果
●Study 1では、公園を対象として、電車の音、鐘の音、子どもの声が魅力・訪問意向・街の居住意向に与える影響を比較検証しました。図1に示すとおり、共通の公園の画像に、電車の音、鐘の音、子どもの声を挿入した動画を作成し、日本の20-60代の2,250人への調査でランダム化比較試験を実施しました。被験者はランダムにその中から1つの動画を視聴したのち、各指標を5段階尺度で評価をしました。その結果、図2に示すとおり、いずれの指標でも、電車の音よりも、鐘の音と子どもの声の方が高いスコアを獲得しました。
●表1に示すとおり、性別(男、女)×年齢(20-44歳、45歳-69歳)ごとに評価の違いを分析した結果、いずれの指標でも、鐘の音と子どもの声を好意的に評価したのは45歳-69歳の男性でした。それに対して、20-44歳の女性は、いずれの指標でも鐘の音と子どもの声に対する評価は他の属性より低くなりました。特に子どもの声への評価が低く、居住意向では電車の音の方が高い評価となりました。
●Study 2では、20-44歳男女を対象として、子どもの有無による「子どもの声」に対する印象の違いを評価しました。図3に示すとおり、街びらきのパンフレットを作成し、処置群にだけ子どもの声を強調する内容にしました。各群500人、計1,000人へのランダム化比較試験の結果、子どものいない20-44歳の女性のみ、子どもを強調した街びらきを有意に低く評価しました。
●この結果の背景には、日本の古い社会制度・価値観が影響していると考えられます。働く20代-40代女性の多数が仕事と出産の両立に悩んでおり、キャリアのために出産を断念する場合すらあります。この悪しき制度が女性を苦しめてしまい、その結果子どもの声を低く評価する可能性があります。
●本研究の結果の示唆は、主に2つです。
(1) 都市政策において、サイレントマジョリティを無視し、ノイジーマイノリティに影響を受けた政策は、全体の評価と乖離する懸念があります。実際、鐘の音や子どもの声に対しては、全体としては肯定的な評価です。市民全体のエビデンスなきまま意思決定をすると、都市の風情や活気が失われていくリスクが大きいです。
(2) 苦情、あるいは低い評価を受けた政策について、その発信元の市民属性とその理由を詳細に分析すべきです。その結果、世間のイメージと異なる実態が浮かび上がる可能性があります。これを見誤ると、適切な対処をすることができません。
論文情報
加藤拓巳・千葉友希・服部亜美・池田亮介・小泉昌紀. (2025). 都市の生活音に対するサイレントマジョリティの印象の可視化 -鐘の音と子どもの声が公園の魅力に与える影響-. 日本感性工学会講演論文集、 2(2)、 1-7.